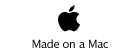質問コーナー

その9(第10回)
Q:太陽も大きくなったり小さくなったりするのですか。
A:多くの変光星は脈動と言って星の半径が大きくなったり小さくなったりすることで光を放射する面積が増減して明るさが変わります。これを脈動変光星と言います。一方で、非常に接近した連星系では相互に食(一歩の星がもう一方の星を隠す)を起こして明るさを変化させる場合があります。これを食連星(食変光星)と言います。
さて、太陽がこれまでに脈動を起こしたことがあるかどうかと聞かれれば確たる証拠はありません。望遠鏡を使った天体観測の歴史は400年にしか過ぎません。その範囲では太陽に大きさの変化なしと言って良いでしょう。ただし、太陽の表面が安定しているかと言えば、実は5分周期で波打っていることが知られています。ただし、この表面の5分振動は太陽の大きさを変化させるようなものではないので明るさに影響はありません。
Q:彗星(ほうき星)は尾を引いていなくても、彗星(ほうき星)と言うのでしょうか。
A:彗星の形態的な特徴は2つ(あるいは3つ)あります。一つは彗星核から吹き出したガスとチリが球状に広がったコマ。もう一つが尾(さらに尾はガスの尾/イオンテールとチリの尾/ダストテールに分かれる)です。彗星核が最低でもコマをまとっていないと、見た目では小さな小惑星と区別できません。もしも軌道が非常に細長い楕円(あるいは放物線や双曲線)であった場合には、太陽系外縁部から来たので彗星核(=彗星)だとわかります。何度も太陽の周りを周回しているうちに、木星や土星など惑星の重力による影響で軌道が変わり、軌道の形では小惑星と見分けがつかない場合もあります。この時でも、過去にコマをまとったような事例があれば彗星だとわかります。ただし、このような古株の彗星核の中には、揮発性物質が枯れてしまったものもあるでしょう。そうなると軌道からも見た目からも小惑星と見分けがつかなくなります。最近では太陽系小天体(小惑星、彗星をまとめて指す言葉)の反射光を分光観測して、その性質から小惑星タイプを分類したりもしているので、その中に、枯れた彗星核と思われるものもあったはずです。
いずれにしても「彗星(ほうき星)」という用語自体、見た目から付けた名称ですので、見た目の特徴を省くと判断は難しくなると言えるでしょう。
Q:光の進行方向が天体の重力で曲げられる時、光は何に対して直進しているといえるのでしょうか。
A:一般相対性理論の質問ですね。相対性を考えるツボは、「誰から(どんな座標系)から誰を(他のどんな座標系を)見た時にどうなるか」ということを意識することです。天体の重力で光が曲げられるという場合、「観測者は天体の重力の影響を受けていない座標系から見ており、天体の重力によって歪められた座標系を進行する“光”を見たら曲げられているように見える」ということです。
さて、この光を天体の重力で歪んでいる座標系から見たらどうなるでしょう。この場合は観測者が持っている物差しそのものが重力場の影響で歪んでいます。しかし、その観測者にしてみれば、その物差しはまっすぐなので、通過していく光は直進して見えるはずです。
まとめると、天体の重力で光の進行方向が曲げられる時、光は天体の周りの歪んだ空間に対して直進している・・・ということになります。
2009年7月7日火曜日