 |
 西はりま天文台の新旧望遠鏡。左が60cm反射望遠鏡で フォーク式赤道儀を架台として採用。右の2m反射望遠鏡 は経緯台式架台を採用している |
経緯台では望遠鏡の方向を上下と左右に回転させて見たいものに向けます。天体を追尾する時は、刻々と変化する天体の見上げる角度と見える方角に合わせて、望遠鏡を上下左右に少しずつ動かします。赤道儀は経緯台をわざと傾けて、例えば左右に回転させる軸を天の北極の方向に合わせて使う仕組みです。望遠鏡の方向を決めるには面倒くさい仕組みですが、もちろん利点があります。赤道儀は見たい天体に望遠鏡を向けてさえしまえば、天の北極に向いた軸を一定の速さで回転させるだけで、簡単に天体を追尾できるのです。天体はほぼ一日で空を一周して元の場所に戻ってきますから、回転は時計の短針の約半分の速さになります。経緯台は見たい天体に向けやすく、赤道儀は天体の追尾が易しい仕組みと言えます。
7.経緯台式架台とインスツルメント・ローテーター
経緯台には天体追尾に伴う問題がもう一つあります。普通に目で観察している分には気にならないかもしれません。しかし天体写真を撮ろうとすると問題が生じます。天体写真を撮る時には、シャッターを何分間も開け、天体からの光をできるだけ多くフィルムや撮像素子(デジカメで絵を記録する半導体素子)に蓄積させなければなりません。経緯台だと天体を追尾したつもりでも、写真の星々は、画像の中央を中心にぐるりとブレて写ってしまうのです。これを視野回転といいます(図11)。
視野回転を無くすための一つの方法は、追尾する時に、カメラも視野回転に合わせて回してやることです。この仕組みはインスツルメント・ローテーターと呼ばれます。逆に鏡を使って視野回転を止める仕組みもあります。これをイメージ・ローテーターと言います。
8.大型望遠鏡には経緯台式架台が良い
こうして二つの架台方式を比べてみると、天文学者が使うような本格的な大型望遠鏡は赤道儀なんだろうなと思うでしょう。事実、少し前まではそうでした。しかし近年になって製作された大型望遠鏡の殆どが経緯台を採用しています。何故でしょう。架台の上に載せる望遠鏡は大型になれば重くなります。その重みは望遠鏡を動かす架台の回転軸にかかってきます。斜めに傾いた軸で重量物を支える赤道儀は、重みによる変形などの影響も出やすく、大型化によって機械的精度を保つことが極端に難しくなるのです。一方で経緯台では天体追尾に上下の回転軸と左右の回転軸、視野回転を止める軸が必要で、回転を刻々と微妙にコントロールする必要が出てきます。しかし架台の軸は水平や垂直の向きになっているので、重量物を支えるには構造的に有利なのです。近年では追尾の面倒さはコンピューターによって解決できます。そうなると経緯台式架台の機械的な利点の方が大きいのです。
9.2メートル望遠鏡をコントロールする
西はりま天文台2メートル望遠鏡には統合制御システムが導入されています(図12)。その目的は複雑なメカニズムを持つ望遠鏡の操作をわかりやすくすることです。やりたい観測方法を選び、観測天体を決め、観測装置の設定を決める。それ以外の必要な操作はコンピューターが自動処理します。
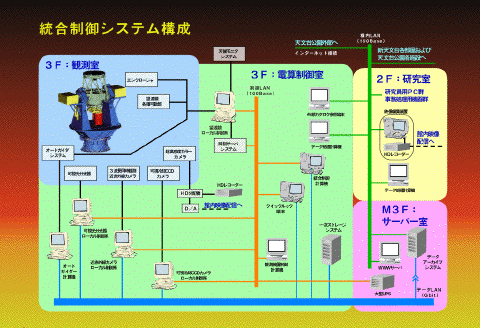
図12:統合制御システムの構成(クリックすると拡大図が出ます)
それでは2メートル望遠鏡の操作方法を説明しましょう(示される画面は実際の操作画面です)。図13は観測者が統合制御計算機の前に座って最初に目にする画面です。
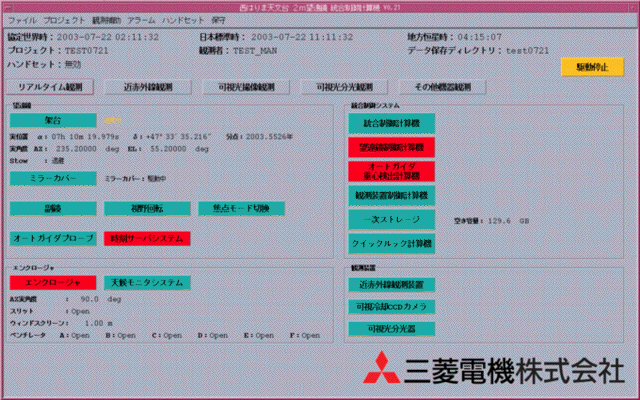
図13:統合制御計算機メイン画面
上の方に5つのボタン(リアルタイム観測、近赤外線観測、可視光撮像観測、可視光分光観測、その他機器観測)が並んでいますね。これが2メートル望遠鏡で行える観測です。この中から例えば「近赤外線観測」を選んでボタンを押してみます。その時に出る画面が図14です。
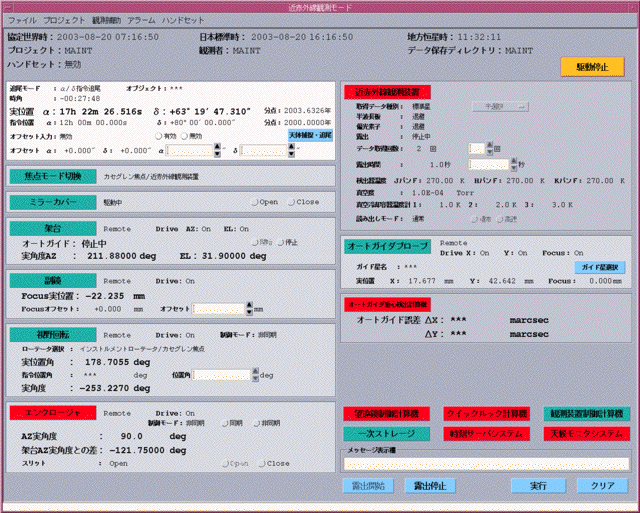
図14:近赤外線観測モードの操作画面
左最上段の囲みで観測天体(望遠鏡を向ける方向)を設定します。その下に並んでいる囲みはいずれも望遠鏡の鏡筒内部の機能やエンクロージャ(いわゆるドームのこと。最近は半球型に限らない一般的な呼び方として使われます)の機能を好みによって設定する部分です。設定しなくても問題はありません。右最上段の囲みは近赤外線観測をするための観測装置(3波長同時観測近赤外線カメラ)の設定を行う部分です。装置の持っている機能を細かく設定することもできますが、基本的には露出時間と撮影枚数(回数)を設定すれば準備完了です。画面右下の「実行」ボタンを押すと望遠鏡と観測装置が設定通りに動きます。続いて「露出開始」ボタンを押せばシャッターが開くという仕組みです。露出が終わると隣のクイックルック計算機に今撮った画像が表示されます(図15)。
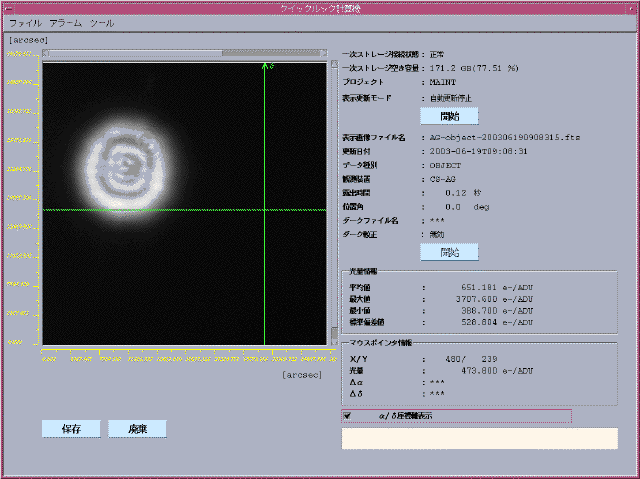
図15:クイックルック計算機の画面
この画面上では画像に単純な処理を施して表示させたり、画像情報を調べることが可能です。
さて、2メートル望遠鏡の複雑なメカニズムを紹介してきましたが、操作はわかりやすそうだと思っていただけたでしょうか。ちょっと難しいデジカメくらいに感じていただければ設計意図は満足されたことになるのですが。
おまけ
最後に本文で紹介しきれなかった統合制御システムの観測操作画面の数々を並べます。
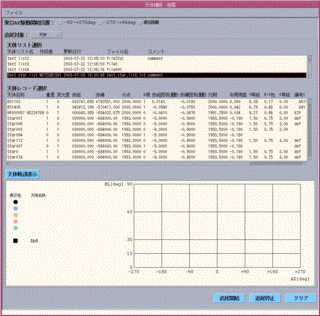 |
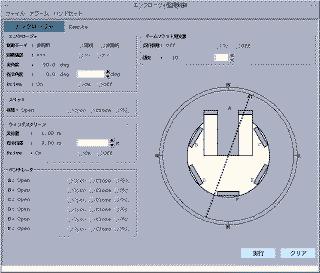 |
| 観測天体選択画面 | エンクロージャー操作画面 |
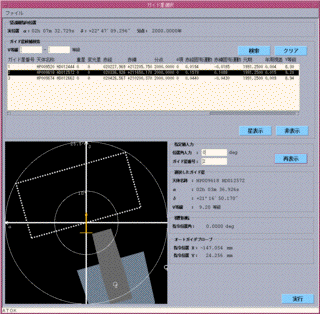 |
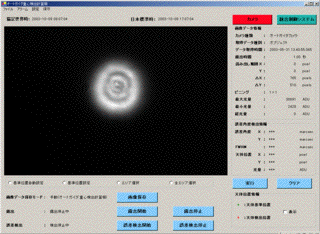 |
| オートガイダーガイド星選択画面 | オートガイダー重心検出計算機の画面 |
|← 前に戻る|