
2025年度の学生と研究テーマ

今年度の学生は、全員で9人!!みんなが自己紹介と、研究の紹介をしてくれるみたいまる〜〜!!
*大学院 博士課程*
D3 岡田 寛子 (Hiroko OKADA)

■自己紹介
わくわくすることが好きです。興味の向くまま精一杯研究したいです。
■研究内容
星を分光(スペクトル)観測すると、その星の化学組成や運動を調べることができます。 星の化学組成には形成当時の宇宙の化学情報が記録されているので、宇宙初期に誕生して現在も生き残っている古い星 を観測することは「宇宙で元素がどのように増えていったのか」や「元素の起源」を調べる手掛かり になります。なゆた望遠鏡を始めとする様々な望遠鏡を用いて(1)宇宙初期の星の探査観測、(2)化学組成に基づいた宇宙初期の研究 を行っています。D2 古塚 来未 (Kurumi FURUTSUKA)
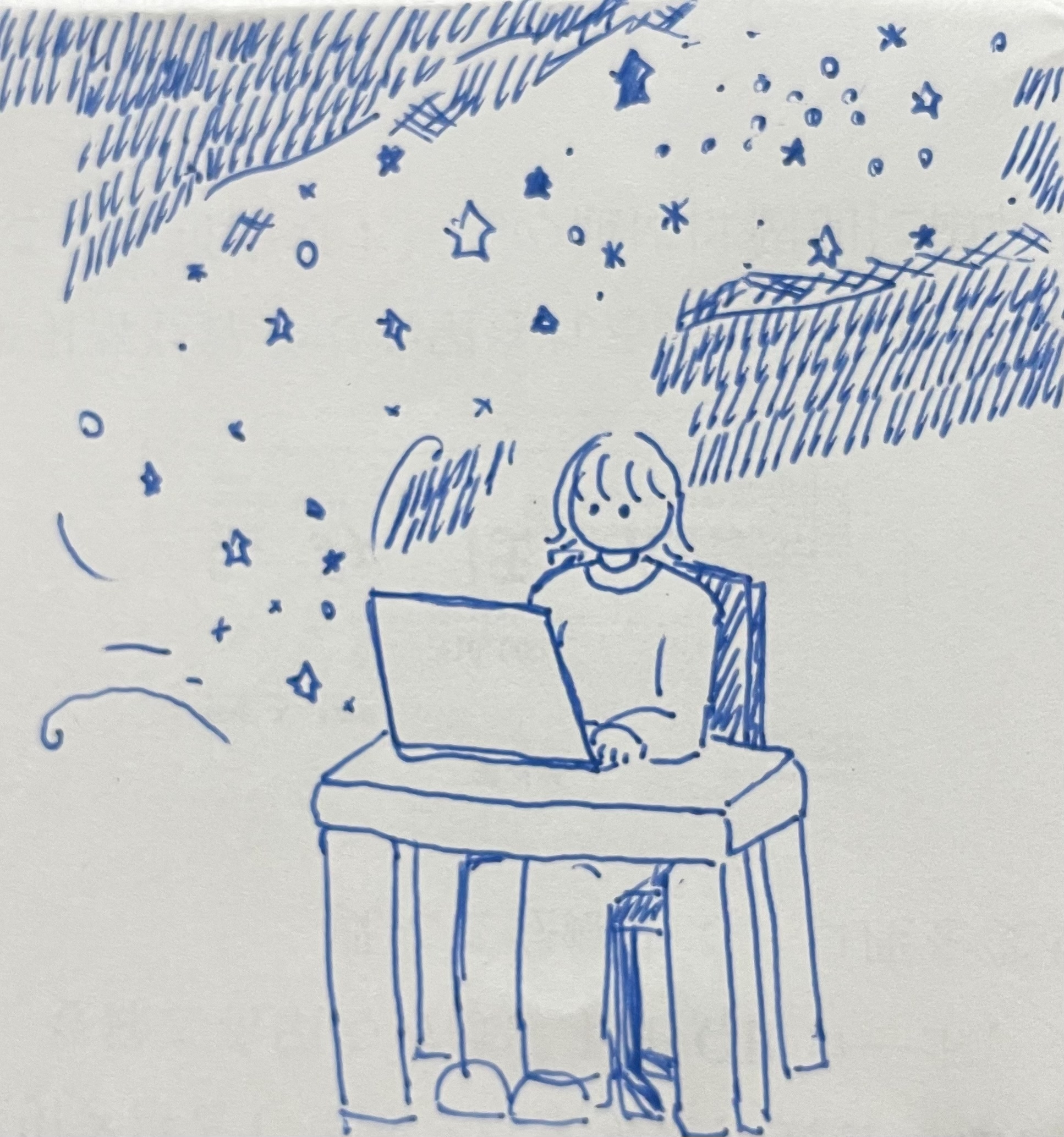
■自己紹介
子どもの頃から宇宙のことが好きで、研究するのが夢でした。趣味は絵を描くことです。
■研究内容
私たちの体や、身の回りにあるものは全て元素からできています。 ではこの元素はいったいどこからやってきたのでしょうか。ビッグバンで誕生した直後の宇宙にはほぼ水素とヘリウムしかなく、 その後、恒星内部などで様々な元素がつくられ、時間とともに元素が増えてきました。一方で、とても重い元素のトリウムなどは、 起源が完全には明らかではありません。この起源を調べるために、恒星の化学組成が手掛かりとなります。恒星の大気にはその恒星が 生まれたときの宇宙の元素組成が保存されるため、重い元素(金属と呼びます)が少ないほど古い星、多いほど新しい星と考えることができます。そこで、 様々な金属量の恒星の化学組成を調べることで、宇宙の中で時間とともにどのように元素が合成されてきたかを探っています。
*大学院 修士課程*
M2 永田 晴飛 (Haruhi NAGATA)

■自己紹介
ラジオとアニメと音楽が大好きです。ジャンプ好き、リトルトゥースは是非話しかけてください!
■研究内容
研究テーマは「活動性の高い恒星の観測」です。太陽はフレアと呼ばれる爆発現象をたびたび起こしていますが、 太陽型の恒星の中には太陽では観測されない巨大フレアを起こすような活動性の高い星があることが知られています。 しかし、恒星の活動の原因は詳しくはわかっていません。そこで、恒星の自転に伴う彩層輝線(Hα線やカルシウム輝線)の変化を調べて、 活動のメカニズムを解明していく研究をしています。
M2 水本 拓走 (Takuto MIZUMOTO)
■自己紹介
小学生の頃から宇宙が好きで、気づいたらここにいました。ラーメンとかも好きです。
■研究内容
私の研究テーマは、「ポストTタウリ型星の探査」です。ポストTタウリ型星は、太陽くらいの質量を持つ、比較的若い星です。 年齢が数千万歳〜1億歳程度で、太陽のような主系列星になる前の段階にあたります(太陽は46億歳)。ポストTタウリ型星はまだ分かっている特徴が少なく、発見数が少ない天体です。 そのため、特徴を解明できれば、新たなポストTタウリ型星を発見できると考えています。
M1 石原 稜也 (Ryoya ISHIHARA)

■自己紹介
すみっコぐらしのとかげを推してます。神社が大好きなので、佐用の神社にもたくさん行きたいです。
■研究内容
研究テーマは「複眼望遠鏡の開発」です。複眼望遠鏡とは、対象天体をたくさんの小型望遠鏡で捕らえ、それぞれの望遠鏡からの光を一つにする 観測システムです。大きな鏡や駆動装置を要しないため、建築コストを格段に抑えながら大口径望遠鏡と 同じくらいの集光力を確保できます。実現されれば、長期間の分光観測を必要とする研究への貢献が期待できます。新たな系外惑星を発見できるかもしれません。
M1 山本 紗貴太 (Sakito YAMAMOTO)

■自己紹介
短い時間で色々な知識を身につけたいです。アクロバットをやっています。
■研究内容
私の研究テーマは「土星の偏光観測とそのための装置開発」です。これまで土星は明るい環からの反射光の影響で惑星本体の状態が観測しづらいという課題がありました。 しかし、今年の11月ごろには土星の環が地球から見えにくくなるので、この貴重な機会に西はりま天文台で観測し、偏光観測という光の向きの情報を調べる手法を用いることで周囲の塵や大気の状態を詳しく分析し、 天候の解明につなげたいと考えています。11月までの期間は偏光装置の開発を行っており、装置の光学実験を重ねて精度の高いデータ取得を目指しています。
*学部生*
B4 足立 仁和花 (Towaka ADACHI)

■自己紹介
映画とか猫とか睡眠とかWEST.とか色々好きです。 好きなものが沢山あります。よろしくお願いします!
■研究内容
私の研究テーマは、「宇宙望遠鏡を用いた散光星雲のPAH探査」です。星雲は、星間物質の密度が高く、星が生まれる場です。中でも散光星雲は、近くの明るい星の光を受けて、 ガスや塵が明るく輝いて見えます。PAHは炭素系の星間物質で、宇宙の様々な環境にいるので、生命起源の候補としても考えられています。 このPAHが星の光を受けて出す輝線を分析することで、その場の環境やPAHの性質を調べます。 この輝線は、地上では大気によって吸収されてしまい観測が困難なので、宇宙望遠鏡のデータを使っています。
B4 小島 楓多 (Futa OJIMA)

■自己紹介
甘いものと外に出かけることが大好きです。 何事も最初から最後まで全力で頑張ります。
■研究内容
私の研究テーマは「太陽系外惑星の大気変動の検出」です。この研究ではトランジット法を用います。トランジット法とは惑星が恒星の前を通過するとき、 恒星の光がさえぎられて、見かけの明るさが一時的に減少することを利用し惑星を検出する方法です。この減光を複数の波長で調べると、大気組成の推定が可能です。 さらに、長時間かつ多期間の観測をすることで、その変動をとらえたいと考えています。これは大気循環や気象現象を理解する手がかりとなり、 惑星の気候や進化を探ることができると考えています。
B4 久米 葵 (Aoi KUME)

■自己紹介
ポケモンが好きです。特にラティアスとラティオスが大好きです。よろしくお願いします!
■研究内容
私の研究テーマは「B型輝線星の観測」です。B型輝線星(Be星)はB型星のうち水素の輝線が見られた星のことです。この輝線は恒星の周囲にある円盤から出ていると考えられています。 この円盤は角度が変わったり消えたり生成したりと変動を繰り返しています。また伴星が近くを通ることでも変動します。伴星が主星の近くを通るときのスペクトルの変化を継続的に観測することによって、 円盤の構造に制限をかけることができると考えています。
